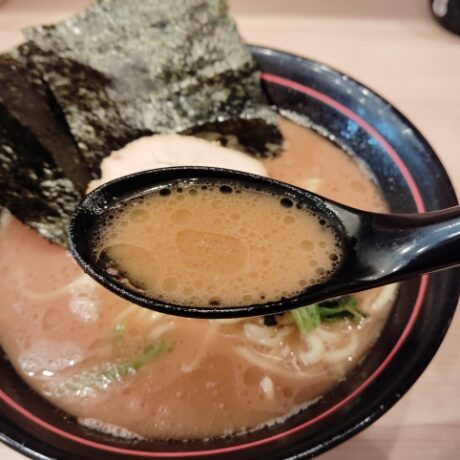夏休みの自由研究や観察日記で育てていた朝顔が、ある日ふと見るとしおれて枯れてしまっていた……そんな経験をしたことはありませんか?
私も3人の子を育てる母として、長女の朝顔を枯らせてしまった経験があります。最初はどうしようと焦りましたが、試行錯誤しながらなんとか夏休みの宿題を乗り切ることができました。
この記事では、朝顔が枯れてしまったときの3つの対応策と、我が家で実際に行った観察日記の工夫をお伝えします。同じように悩む親御さんのヒントになれば嬉しいです。
朝顔が枯れた時の3つの対応
朝顔が枯れてしまったら、まずは親子で落ち着いて状況を受け止めましょう。枯れたという事実も、立派な観察の一部。対応次第で子どもの学びにつながる経験になります。
- 枯れた様子も観察対象とする
- 同じ種類の朝顔を再度育ててみる
- 図鑑や資料を活用して補足する
1つ目の対応:枯れた様子も観察対象とする
朝顔が枯れてしまっても、その変化を観察対象にすることで、観察日記として成立させることができます。たとえば以下のような視点が役立ちます。
- いつから様子が変わったのか?
- 葉っぱの色や形にどんな変化があったか?
- 水やりや置き場所に問題はなかったか?
植物が枯れていく様子を丁寧に記録することで、「成長の終わり」まで観察できた立派な自由研究になります。
2つ目の対応:同じ種類の朝顔を再度育ててみる
もし時期に余裕があれば、園芸店や100円ショップなどで朝顔の苗を再購入し、観察を続けるという手段もあります。
- 日数が足りない場合は、1週間分だけでも記録する
- 写真で成長過程を補う
- 育て直した理由を正直に書く
観察日記には、やり直しの経緯を書くことで「失敗→再挑戦」という学びの姿勢を伝えることができます。
3つ目の対応:図鑑や資料を活用して補足する
観察が続けられない場合は、図鑑やインターネットを利用して、知識を補うという選択肢もあります。図書館で朝顔に関する資料を調べるのもおすすめです。
- 成長過程や開花の様子を図鑑で確認
- 花の色や形、種のつき方などを描写
- 「本で知ったこと」と「自分の育てた朝顔の違い」などを記載
この方法では、子どもが主体的に調べて記録する力を伸ばすことができます。
我が家の体験談
我が家では、長女が育てていた朝顔が、8月中旬に完全にしおれてしまいました。葉が茶色くなり、茎も細くしぼんでしまって、どうにも復活できそうにありませんでした。
最初は涙ぐんでいた娘ですが、「どうして枯れたのかを一緒に考えてみようか」と声をかけて、親子で朝顔の記録を振り返りました。
その後、近くの図書館に行き、朝顔に関する図鑑を数冊借りて、一緒に読みながら観察日記の続きを書いていきました。
我が家の日記の事例
長女の日記には、以下のような内容を記録しました:
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 8月1日 | 葉っぱが少し黄色くなってきた。水やりは毎日している。 |
| 8月5日 | 花が少ししか咲かない。日当たりが悪いのかもしれない。 |
| 8月10日 | 葉が茶色になり、茎も元気がなくなってきた。 |
| 8月12日 | 完全にしおれてしまった。図鑑で朝顔の枯れる原因を調べた。 |
娘は、「水やりはしていたけれど、風通しが悪かったかも」「鉢が小さすぎたのかもしれない」と、自分なりに原因を分析していました。
図鑑に載っていた花の写真を参考にして、思い出しながら絵を描き、特徴を書き足して完成させた観察日記には、先生から「工夫してよく調べたね!」というコメントをもらえました。
まとめ
朝顔が枯れてしまうと、親としてはつい焦ってしまいがちですが、子どもにとっては大切な学びの機会でもあります。
- 枯れたことを正直に書いてOK
- 図鑑や資料を使って調べたことも評価される
- 親子で工夫すれば「体験」として価値がある
無理に成功体験に仕立てなくても、観察の過程を丁寧に振り返ることが、夏休みの自由研究の本来の目的なのかもしれません。